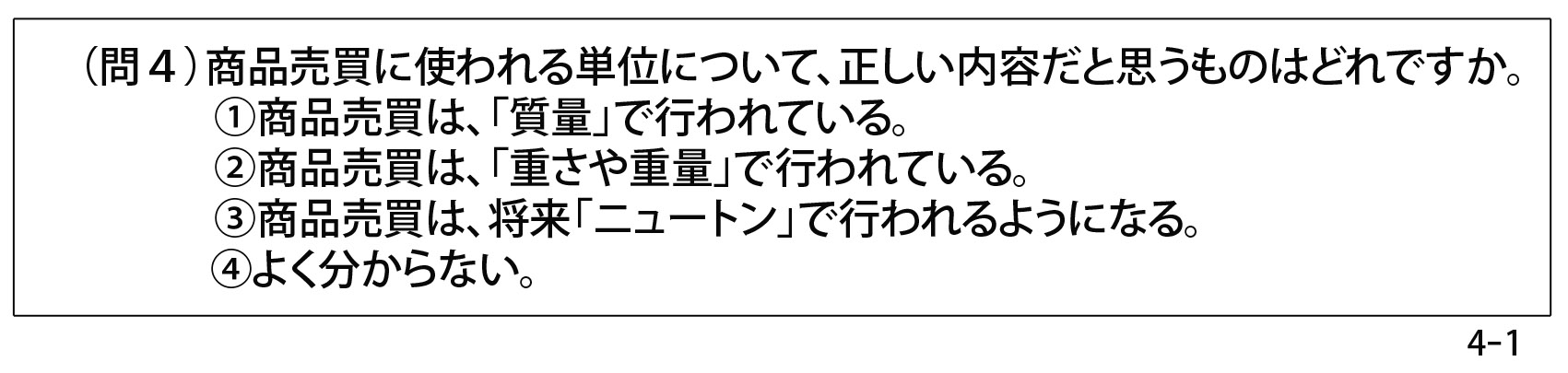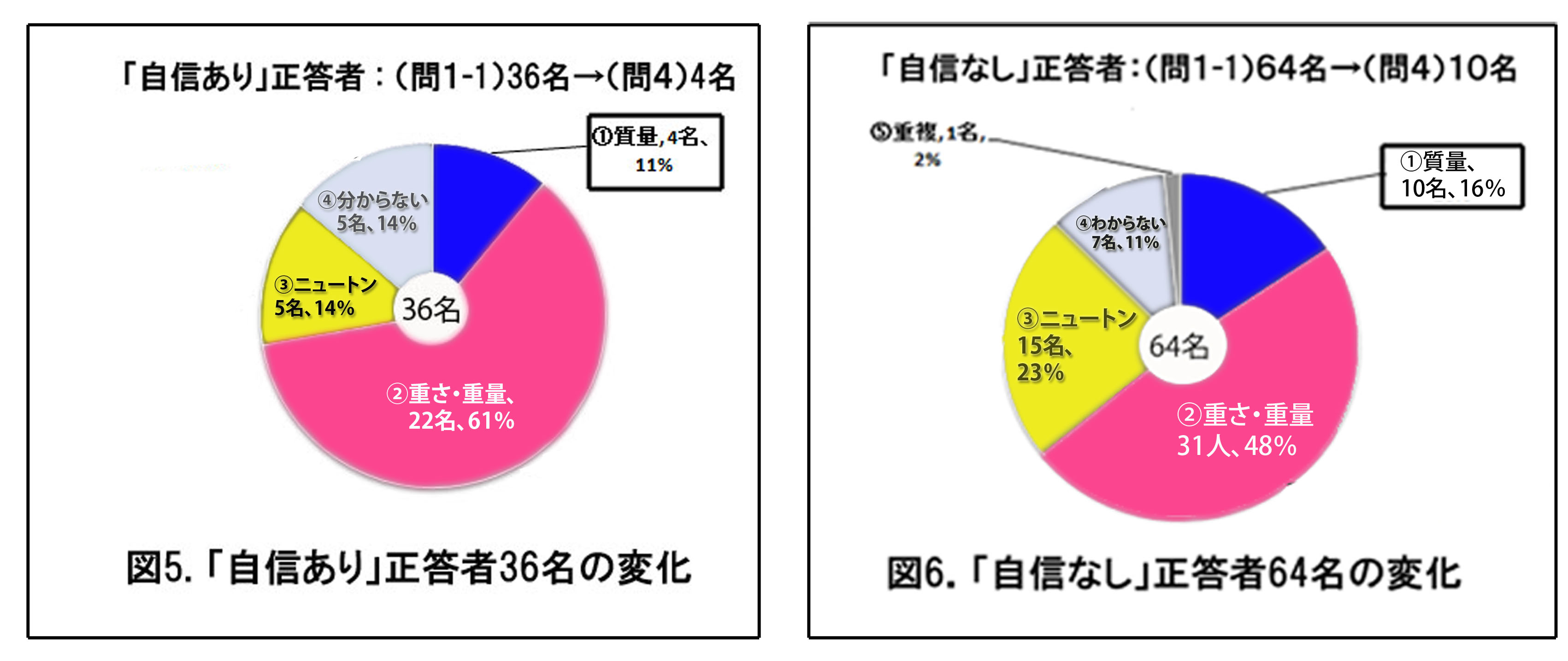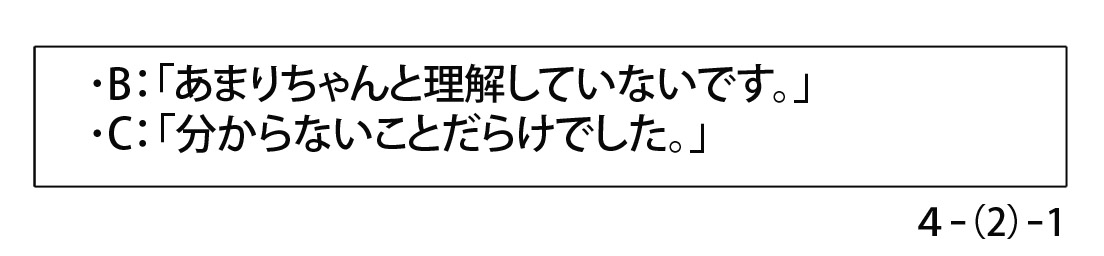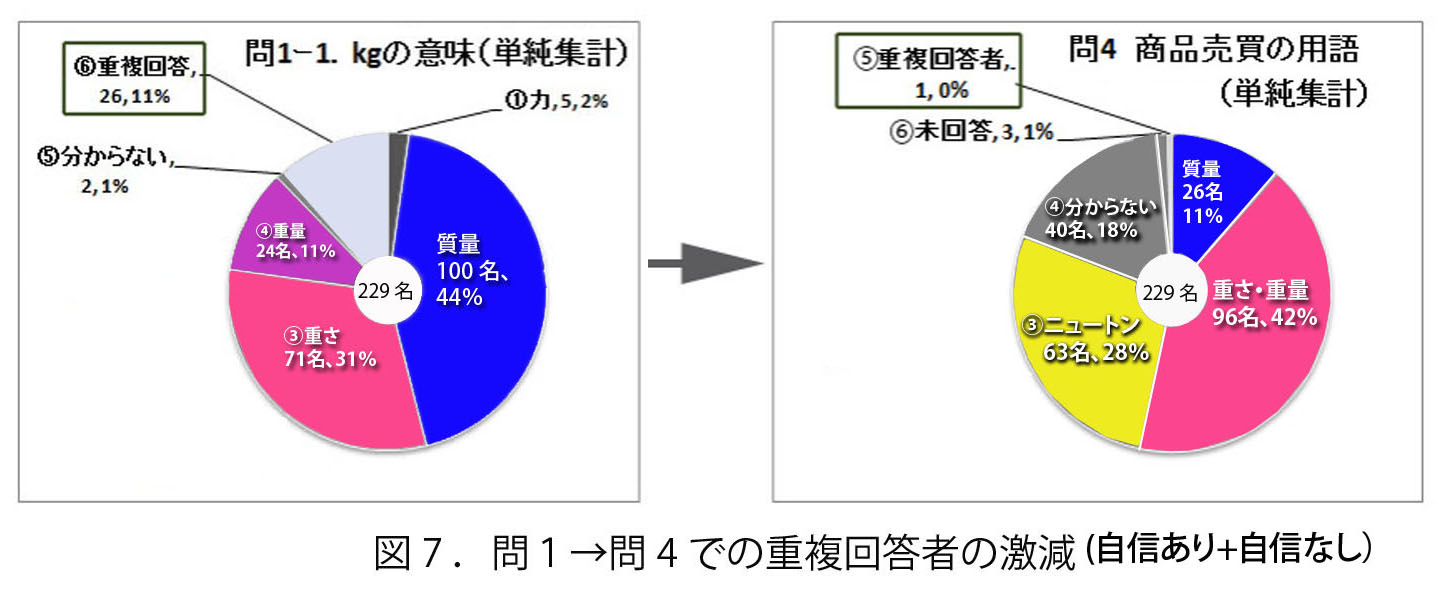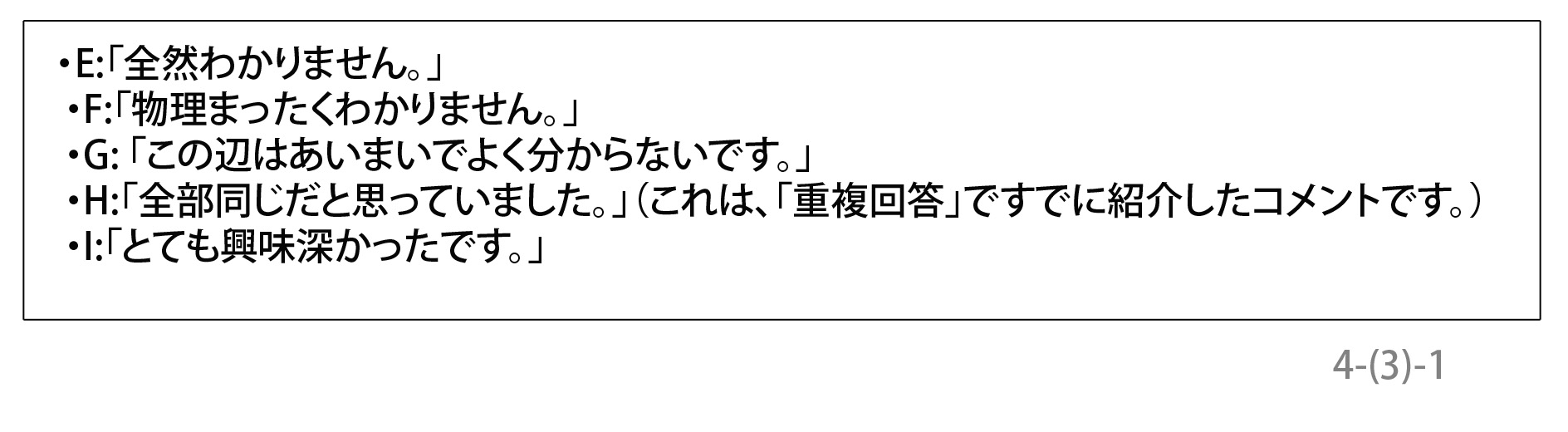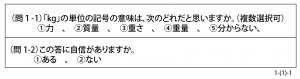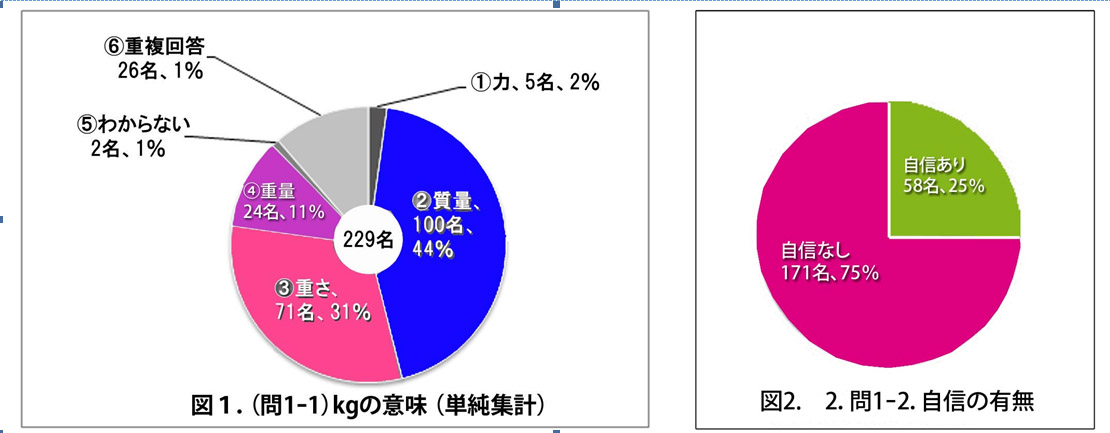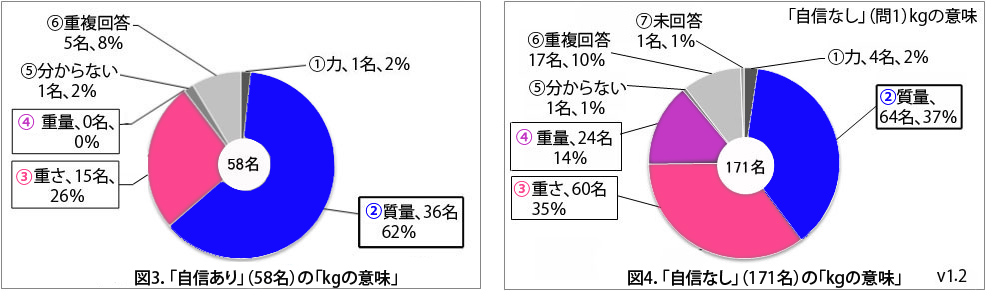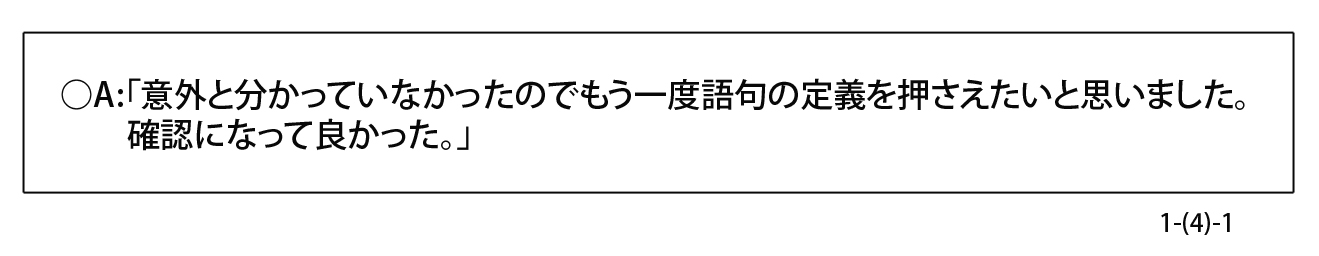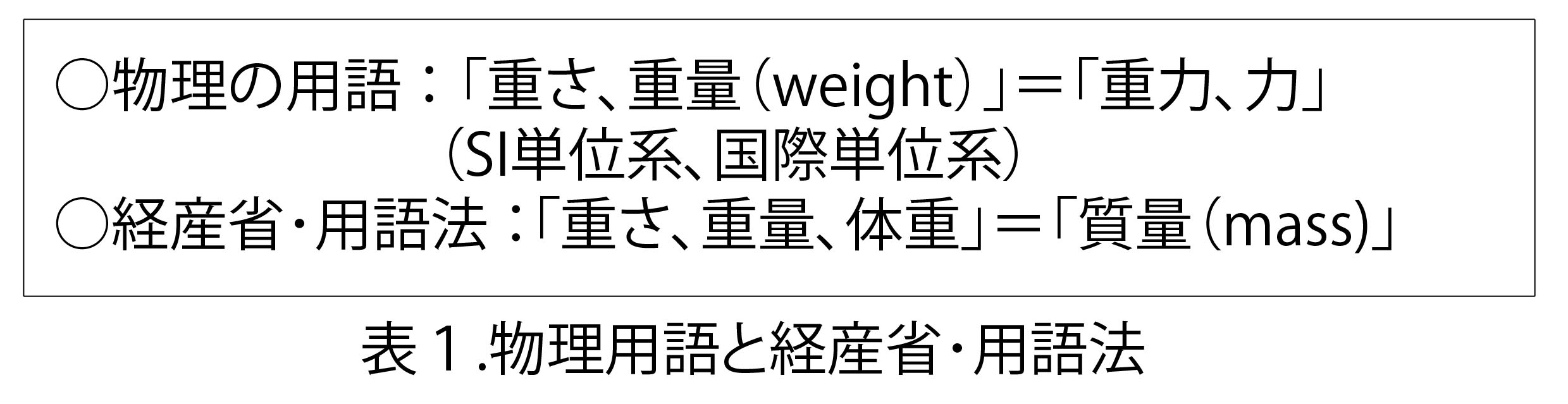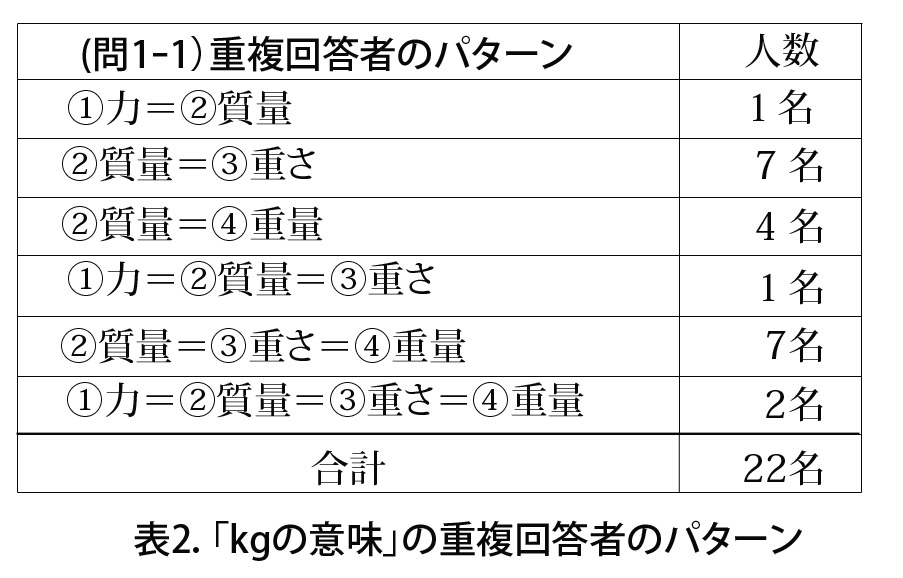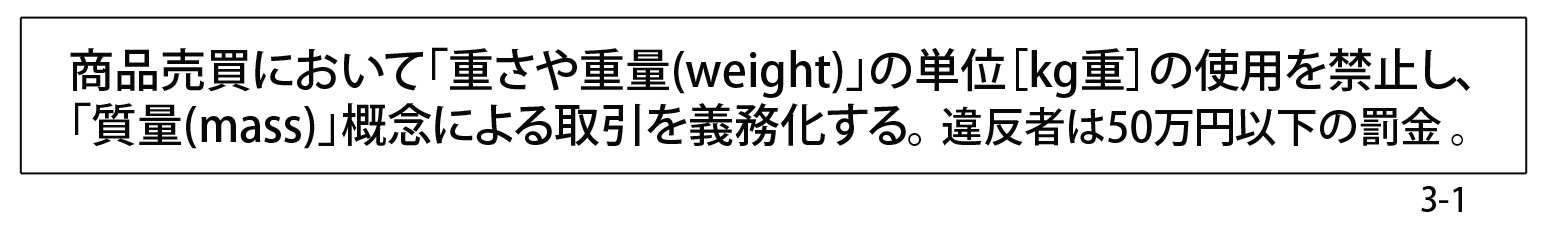『近代日本一五〇年──科学技術総力戦体制の破綻』(山本義隆著 岩波新書、2018.1)
科学技術幻想の終焉と現代史の新たな歴史観
元『科学・社会・人間』編集委員 福島 肇
(岩波新書、2018年1月刊、
320頁、1,015円+税)
◆人間を自然の主人公に置く科学の思想-150年にわたる科学技術幻想
人間が自然を拷問にかけて自然に自白させる、それが研究の正しいやりかただ(ボイル)。新科学のもたらす「実践的哲学」によって、「私たちは自然の主人公で所有者のようになるでしょう」(デカルト)。近代の哲学と科学は人間を自然の外に置いた。人間は「上から目線」で自然を見るようになった。
近代以前の西欧世界では、自然は有機的で生命的な全体であり、人間はその一部として自然に調和して生きていると考えられていた。技術は[16世紀までは]自然に劣るものと見られていた。
以上、本書からの引用であるが、17世紀始まった近代科学が、19世紀、技術と結びつき、科学技術による自然の征服という思想があたりまえに思われるようになった。
西欧に発生した科学技術は資本主義とともに、世界を席巻してきた。だが、それはひとつの思想・イデオロギーに過ぎない。
それを明治、日本で引き継いだ代表が福沢諭吉である。福沢の「自然は完全に合法則的であり、人間精神は無限ゆえ科学によって解明しえないものは何もないという、近代科学への絶対的信頼」(『文明論の概略』6)は、技術の可能性への過大な期待へと繋がる。
誰か山を祭る者あらん。誰か河を拝する者あらん。山沢河海風雨日月の類は文明の人の奴隷と云ふ可きのみ。(『概略』7)
文明の人とは技術を持った人。自然はその「奴隷」とされる。福沢らが囚われていた過大な科学技術幻想が、以後150年間、日本を呪縛したとされる。
◆黒船から福島まで
本書の帯にこうある。本書は、前述した著者の近代科学技術への認識を背景にした、明治維新から福島原発事故までの近代日本150年史である。次のように分けられるのだろうか。
1.明治の「殖産興業・富国強兵」、1910年代、産業革命の終了
2.アジアでただ一国の帝国主義列強への仲間入り、朝鮮・中国などの侵略
3.総戦力体制の構築、科学技術体制の軍事化
4.アジア侵略戦争・太平洋戦争下の「総戦力体制による高度国防国家」
5.敗戦後の列強主義・大国主義ナショナリズムに突き動かされた「経済成長・国際競争」
6.福島原発事故による破綻
これらが、「科学技術総力戦体制」という共通項でくくられ、連続しているものとしてダイナミックに語られる。
明治の科学技術の導入は、市民社会の未成熟もあり、民主主義・人権思想抜きに、官と軍により、軍事中心になされた。この日本的な科学技術の特質が戦前・戦中から戦後と一貫して続いて行く様子が、本書では詳細な資料を基に緻密に描かれる。
150年の歴史の基軸とされるのは、資源とエネルギーの確保であろう。日本の産業革命は電力(電気エネルギー)の工場での利用(1910年代半ば)で完了したとされる。そして、総力戦体制のための新たなエネルギーと資源を求めて、日本は朝鮮侵略からアジア侵略・太平洋戦争へと進んでいく。
なお、資源という面での象徴的な発見はハーバーとボッシュによる空中チッソの固定法とその工業化(1909,1913)であろう。これは肥料や火薬が、硝石がなくても作れるようになったことを意味する。「資源小国」日本では、これが「無から有を創造する」(船山信一・哲学)などととらえられる。
なお第一次大戦は最初の科学戦で、毒ガス、戦車、航空機などが使われた。それが日本に大きな影響を与え、科学技術は文字通り軍事と一体化してゆく。
戦後のエネルギー多消費社会(裏では軍需産業が発展)の分析をへて、終章で原子力(核エネルギー)について詳しく述べられる。核エネルギーの民生利用が、軍事利用に不可欠なこと、それゆえ民生利用が導入されたこと、日本が潜在的核保有国であることだけ確認しておく。
なぜ科学技術総力戦体制が福島原発事故で破綻したのか。ひと言で言うと、明治とともに始まったエネルギー革命(蒸気・電気エネルギー)が1970年代中期の高度成長の終焉で行き詰まり、核エネルギーにまで手を出したことによる福島の事故でオーバーランしたということ。
日本のエネルギー消費のピークは2004年。その後、エネルギー消費は減少している。20世紀後半の資源多消費型の基幹産業が今では衰退産業に向かっている。原発はとっくに必要性を失っていた。福島原発事故は科学技術幻想破綻の象徴である。
また、明治以来増加してきた日本の人口は2011年から減少に転じた。これは資本主義の経済成長の条件が失われたことを意味するとされる。もはや経済の成長を維持しなければならない時代は終わった。
◆学者たちの軍事への協力
本書では、明治以来の大学組織と大学人など研究者の軍事との結びつきにも触れられる。
・海軍省の要請による東大の造船学科設立(1884)。造船の研究は軍艦の研究。
・帝国大学での造兵学科と火薬学科の増設(1887)。
これは「西洋の大学でもあまり例のないこと」(中山茂)。
「日本の軍事力は明治期をつうじて[国防から]対外侵略のためのものへと変貌していく」が「学者はその過程になんの疑問もなく追随していく」とされ、田中館愛橘(物理学・東京帝大教授)にその例をみることができるとされる。田中館は日露戦争が始まるとすぐ航海に重要な地磁気データを海軍に送付。航空機の軍事的重要性を貴族院有志に訴え(1915)、それが東大付属航空研究所創設、航空学科(工学部)等の新設につながった。東大総長、山川健次郎(物理学)も航空機研究に熱心であった。
戦時中積極的に軍と官僚に迎合した例としては菊池正士(物理学・量子力学の正しさを裏付ける電子線回折の実験で内外で有名)が挙げられる。菊池は「「大学の自治」や「研究の自由」の理念の完全な放棄による、軍・産・学の共同による研究の一元的支配とそのことによる研究体制の徹底した合理化」の構想を述べている(1941)。
そのほか仁科芳雄(物理学・理研)らによる原爆研究などきりがない。
◆思想家たちはなぜ誤ったのか-教訓
著者は、思想家たちの科学技術体制、社会・経済認識の問題も鋭く指摘する。
世界恐慌後の時代、軍人や官僚は総戦力体制構築のため、統制経済の下での近代化・合理化を進める。この統制経済が、左翼知識人にまで、社会的進歩を意味するものと受け取られていたとされる。
相川春喜(技術論・マルクス主義)は「技術統制の確立が望まれる」と言い、麻生久(東大新人会創設会員・社会大衆党国会議員)は統制を社会主義への前進として評価。日本資本主義の封建的要素を強調する講座派経済学者に限らず土屋喬男(経済学・労農派、東大教授)は近衛新内閣の統制経済政策を評価(1940)する。
「当時日本ではマルクス主義経済学は非イデオロギー化され、大国ソ連の・・・最も実用的な計画経済の理論とみなされていた」(三谷一太郎2017)とあり、統制経済は評価されていたとされる。
戦前・戦中と戦後を通した典型的な知識人の例は小倉金之助(民主主義科学者協会初代会長・数学史)である。小倉に代表される科学と民主主義の同一視は、戦中には総戦力体制に取り込まれ、戦後は科学主義立国に呑みこまれてしまった。戦争のための軍と官僚による統制経済の下で科学技術研究の合理化に対し、「封建制・前近代性に対して合理主義と科学的精神を対置しただけの・・・多くの批判はその無力を露呈する」とある。
最後に大河内一男(経済学・東大闘争勃発時の東大総長)を挙げる。大河内は産業報国会にたいする政府の通牒が・・・「能率増進」とともに「待遇、福利、共済、教養」その他を挙げていることにたいして「・・・我が国の労働史上極めて革新的な出来事」と評価している(1940)とある。
「合理的」であること、「科学的」であることが、それ自体で非人間的な抑圧の道具ともなりうるという著者の指摘は教訓とすべきと言えよう。
◆科学技術総力戦体制がもたらした植民地での弱者抑圧
本書では科学技術と資本主義・帝国主義の発達の過程で必然的に起こる、社会的な矛盾(弱者の犠牲・農村・漁村共同体の破壊、環境破壊など)も取り上げられる。
明治の酷使された女工、足尾鉱毒事件。日中戦争以降の、工場、炭鉱などでの過酷な労働。大戦下、朝鮮人を中心とした外国人の過酷な労働(朝鮮人強制連行 72万5000人)。戦後の水俣病、四日市喘息、三里塚、沖縄など。
特に注目すべきはアジア侵略下でのアジアの人々の抑圧である。植民地が総戦力体制の実験場となった一例が挙げられる。朝鮮半島での巨大な水力発電所群のためのダム建設(鵬緑江、水豊ダムの貯水湖の面積は琵琶湖の半分)がそれである。1万数千戸、数万人の朝鮮人・中国人の強制移住、現地の人々の過酷な労働などが挙げられる。これは、日本帝国主義のアジア抑圧のほんの一部である。なお、この電力と化学工業の巨大コンビナート建設の中心にいたのは「チッソ」である。窒素肥料工場=火薬工場であることも忘れてはなるまい。
◆現代史への新たな歴史観
本書が提示する大きな論点は、「戦後、日本は民主的平和国家へと変わった」というような歴史観への疑義であろう。世界史の見方の転換であると言ってもよい。著者は、第2次大戦とその後の歴史について、ファシズムに対する民主主義の勝利と見る歴史観にかわり、戦時総力戦体制による社会の構造的変動とその戦後への継承と見る歴史観を提示する。明治、戦前・戦中と戦後は連続していると言うのである。
こうした歴史観は山之内靖により1990年代から語られ始めている。ニューディールによる経済統制もファシズムによる経済統制同様、総力戦体制による社会の編成替えととらえられる(山之内)。
山之内は、戦中は「戦争国家=福祉国家」であったという。総力戦のためには、優れた兵力・労働力としての民衆の「豊かさ」、健康が必要である。食糧管理制度(1942/小作農制度の形骸化)、国民健康保険法(1938)はそうした目的をもって戦中に作られ、戦後に引き継がれた。官僚組織もそのまま生き残った。
科学技術でも同様である。「研究資金をはじめ今日の科学研究体制は、すべて戦争を本質的契機として形成されてきた」(広重徹『科学の社会史』1973)。戦時下に創られた科研費、大学院制度、研究機関や理工系学校もほとんどそのまま生き残っているとある。
著者は、健康保険制度などが、軍事目的であったからいけないと言っている訳ではない。「日本の近代化の悲劇」は「軍国主義の進展という社会条件のもとでしか始まらなかったという点に求められる」(広重)と言う。
明治維新から150年、私たちは自分の歴史観と自分の立ち位置を再度吟味するときに来ていると言えよう。
◆科学技術者の軍事研究、戦争総括から現在
戦前・戦中、科学技術総動員体制のもと、科学者、技術者は何の抵抗もなく軍事研究を行ってきた。戦後その反省の言葉は見られない。科学力で戦争に負けたというのが戦争総括であり、敗戦後「戦争のための科学」を「日本再建のための科学」と置き換えただけである。
そして、科学者・技術者は戦後どうなったのか? 一時的に日本の非軍事化を目指したアメリカは、朝鮮戦争で日本の兵站基地化を進めた。自衛隊の創設と相まって、戦中の軍事技術者は、復活した三菱など戦中の軍需産業のもとで、軍事研究を行っていく。戦後の軍事研究・軍需産業は「高度成長」などの民生部門に隠されていたが、アメリカからの技術導入から独自技術の開発へと、明治と同様な形で急速に進められてきた。
安倍内閣は2014年、武器輸出を全面解禁した。民事部門で経済成長を望めないなか、軍需産業は財界と政府によって「日本経済の牽引車」として期待されている(経済の軍事化)。既に大学に軍事研究が要請されており、研究者は再び「科学動員」に直面している。
私見では、出所が軍事だろうと研究費のみ欲しがる科学技術者に軍事研究の拒否を期待することはできない。民衆のがわからの、大学科学者・技術者への異議申し立ての継続が必須である。
◆戦後の大学研究者の責任と学生たちの異議申し立て
熊本水俣病では、旧帝大の科学者が産業界と官庁と一体となって事件を隠蔽・矮小化しようとした。三池炭鉱爆発事故でも同じ。常に、企業と国の側に付く旧帝大の科学者達。私の感想では福島原発事故のとき、事故や放射性物質による被ばくをたいしたものではないとマスコミで繰り返す学者たちは、結果として反面教師となった。人々は「権威ある」「専門家」(科学技術者)をもはや信用しなくなった。
1968-69年の学園闘争は「科学技術性善説」と「成長信仰」の見直しを訴えていた。1968-69年、東大闘争で自然に広がった「東京帝国主義大学解体」というスローガンは的を射ていた(『私の1960年代』)。先述の大河内一男が東大総長であったのは象徴的である。
学生たちの異議申し立てをしっかり受け止めたなら、大学研究者の変革の契機になっただろう。だが、大学研究者は機動隊(国家権力)の導入で答えたのみ。自己変革の契機を失った。
◆これからの展望
福島原発事故により、エネルギー革命に始まった、大国主義ナショナリズムと結びついた科学技術の進歩にもとづく生産力の増強と経済成長の追求という150年の歩みから決別すべきときが来たとされる。
では、著者が示す現在取るべき方向は何であろうか。塩川喜信(『高度産業社会の臨界点』1996)を結論にかえるとある。要旨をおおざっぱにまとめる。
1.市民社会が発達し、国家・市場経済への統制力を増した
2.国家の枠組みの相対的低下、国境を越えた市民社会、民衆の国際的交流・連帯が、戦争の防止、多国籍資本の監視、国境を越えた環境保全等を可能とするシステムを遠望している
3.先進諸国の「失業なきゼロ成長」社会へのソフトランディング、グローバル化する資本と国家への対抗軸は、こうした構造のなかで育まれる
4.エンゲルスの「科学的」未来像はあるべくもないことを実感し、「ユートピア」的発想を、民衆の努力・運動・将来的社会のビジョンの提示によって少しでも実現可能とすることが私たちの課題
著者の言うように市民社会の発達から未来が望めるのか、あるいは格差拡大・中産階級の没落により、変革主体が失われるのか、疑問は残る。
また、著者は科学技術の「産官軍学複合体」は、20世紀の「科学の体制化」(広重)のより進んだ形態として、21世紀の「リバイアサン」として私たちの前に登場しているとする。「では、どうしたらよいのか?」という問いへの答は前述までである。
ともあれ、不勉強な私には知らなかったことがたくさんあった。読めば必ず、何か発見があるであろう。
ふくしま・はじめ
1945年兵庫県生まれ。1971年東京大学教養学部基礎科学科卒業。小平錦城高校教員を務める。「教師は生徒から学ぶ」がモットー。創作科学読み物『光の探検』で1984年度東レ理科教育賞受賞。「物理学者の社会的責任」サーキュラー『科学・社会・人間』編集委員を務める。著書に『物理のABC』『相対論のABC』『電磁気学のABC』『パズル・物理のふしぎ入門』(いずれも講談社ブルーバックス)など。
(『季刊現代の理論』初出)
ホームに戻る