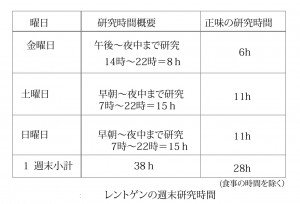レントゲンとX線のリスク意識(最終回)
9.レントゲンの無言の告白
レントゲンは、科学的に実証されていないことについての発言には、非常に慎重である。例えば、ジャーナリストからX線についてのこれからの見通しの発言を求められても、レントゲンは、「科学者は、予言者ではない。」という理由から拒絶の態度をよく示している。
レントゲンが生きた19世紀末の科学者は、まだ中世に見られる神の書記官としての存在を色濃く引きずっている。現象の全貌を発掘し、明らかになった事実を体系的に整理し神殿(学会、図書館)に奉納する。この仕事が科学者として最も神聖で最優先すべきものと考えられていた。「世俗」と一線を画す「無謬性」が科学者・レントゲンの行動原理そのものであっただろう。では、「科学的検証」を経ていない「X線の防護」について、レントゲンはそれをどう社会に向かって語るのだろうか。
X線の研究を始める前のレントゲンは、「科学の無謬性」と「科学者の倫理性」の間に予定調和が約束されていると信じて科学者の小道を誠実に歩いている。レントゲンは物理学の巨匠クントに才能を見いだされ、物理学の研究に打ち込み、科学者として幸福で満ち足りた日々を送っていたが、X線の発見以来だんだん彼の学者人生の歯車がきしみ始める。
レントゲンはX線の存在を科学的に追求する過程で、火傷を負いX線が人間を傷つけることを体験する。そして、より高性能のX線発生装置を開発して行くにつれ、X線障害をさらに深刻化していく未来が、レントゲンからはあらわに見えてくる。「科学の無謬性」にもとづいた「X線の発見」は、科学者・レントゲンにとって輝かしい業績となったが、今度はその「科学の無謬性」が「X線防護」についてレントゲンの口をふさぐことになった。
1896年1月1日のX線発表後、レントゲンは今まで体験してこなかったジレンマに悩まされ始めただろう。洪水のようにやってくるX線の賛辞と非難や嫉妬、予期せぬ怪しい来客、興味本位にX線写真を取り上げるジャーナリズム。これらは、いずれも徐々に通り過ぎる一過性の嵐のようなものだが、レントゲンの内部には日を追うごとに深く入り込んでくるジレンマの存在が成長しつつあったと思われる。それはX線によって火傷を体験し、トタン小屋によってX線からわが身を防護し、なんとか実験をのりきったレントゲンが、今度はX線に無防備な研究者、大衆が被ばくするのを何の策もなく見つめなければならなくなったからである。これは、驟雨のように一過性で通り過ぎることではない。
X線発表後のレントゲンのもとには、X線の追試に成功した報告が次々に伝えられ、学者としての信頼性が日に日に高まっていくのに、彼は不機嫌な毎日を送っている。X線の記事が大衆雑誌に掲載されるのを見るにつけ、レントゲンは不快感をあらわに示し、「素人の人と広く議論をすべきでない」(『レントゲンの生涯』W.Robert Nitske , 考古堂、P19 )という科学者としての持論を吐露している。
そして X線を公表した約1ヶ月後、意を決っしたかのようにレントゲンは大衆雑誌記者ダムからのインタビューを受け入れる。「トタン小屋」を公開し、どのようにX線の実験が行われたかを明らかにする行動を起こしている。実験物理のプロであるレントゲンは、ひやりとする被爆体験をしながらなんとかX線障害をかわしたものの、他方であまりにX線の被ばくに無防備な科学者・大衆を見るにつけ、それを見過ごすことができずに自分に苛立っている。あるいは、「X線の負の発見者」でもある自分に対して、「社会的責任?」というものを予期せず発見して、躊躇しているようにも見える。
トタン小屋の存在の公開には、どこかそうしたやむにやまれずとった行動の風情がただよい、この公開を通して、 レントゲンは「無言の告白」をしているように見えてくる。<わたしは、こうしてX線からわが身を守りました。>ーーーと。
10.創造的知性と負の遺産
レントゲンのトタン小屋の公開記事は、McClure’s Magazine,1896年4月発行の雑誌に掲載されたが、その記事に対して研究者や大衆の反応はどうだったのだろうか。X線の公表から3ヶ月になろうとするこの頃、高性能なフォーカス管はまだ本格的に出回っていないが、クルックス管による火傷や潰瘍の発症者は確実に出始めている時期である。雑誌発行は、タイムリーな時期であるのだが、レントゲンのトタン小屋に対する市民・研究者からの反応は、文献でみるかぎり何も起きていない。
少なくとも、インタビューの記事を読んで、X線の実験のたびに「トタン小屋」に逃げ込んでいたレントゲンに対して「臆病者!」「弱虫!」という非難は投げつけられなかった。大半の大衆は、恐らく「トタン小屋」の裏の意味が理解できなかっただろう。しかし、X線関連の研究者、放電管の製作職人、モデルなどでX線障害をすでに発症した人々は、恐ろしいX線から身を守ってくれる「トタン小屋」の象徴的意味をはっきりと理解しただろう。「レントゲンは、トタン小屋に守られていたのか!」と。
この頃は、X線障害者もX線に不安を抱く研究者もまだ圧倒的に少数で、しかも社会はあげてまだ「神秘的なX線」に浮かれている。社会の圧倒的多数は、このブームに水を差すようなレントゲンの「トタン小屋」に関心がなかった。もっと率直に言えば、X線障害のことなど今は、知りたくなかったのかもしれない。
ダムとのインタビューの後もレントゲンは非難されるどころか、逆に名声は高まる一方でひっきりなしに叙勲や名誉会員や名誉教授の知らせが舞い込むようになる。レントゲンは栄誉の知らせを慇懃に受けるがそれに対して返礼に出かけることも講演をすることもしない。万事がこんな調子で社会とレントゲンの溝は深まるばかりである。X線の不思議な能力に目を奪われているジャーナリストや科学者からは、感激を分かち合おうとしないレントゲンのふるまいをみるにつけ、彼がだんだんKYな性格で人間嫌いな人物と見なされてくる。(また、ほとんどの「レントゲン伝」でもそのように描かれてしまっている。)
レントゲンは、X線に関する最後の論文「第3報」を1年間かけてまとめ1897年3月10日にプロイセン科学アカデミーに投稿している。彼はここで1年半にわたるX線研究だけでなく研究活動そのものにも終止符を打っている。その後、学生の教育、後進の育成、学内の運営などの実務に専念し、レントゲン自身が手におえないほどに膨張した「科学者という虚構」から脱皮をはじめている。
こうして1年半足らずの期間に体験したレントゲンのX線をめぐる「創造的知性」と「負の遺産」のジレンマの話は終わるが、21世紀の原発事故をめぐる科学者においてこの種の問題はさらに深刻化して継承されているように見える。それは、「創造的知性の側に立つ人」と「負の遺産の側に立つ人」の間でさらに分業が徹底され、多くの科学者はより洗練された虚構に自己を同一化し、一個人が抱えていた倫理的ジレンマの所在をしばしば見失ってしまっているからだ。そしてその分だけ科学者という職業が、どこか無責任さを秘めた職業になりつつある。
*「レントゲンとX線のリスク意識」の連載記事は、途中工事などで中断しましたが、これで一応の完成になりました。
無責任さを秘めることなく科学者として生きていけない時代がやってきている。そのことに最初に向き合うことになったレントゲンの生涯は、現在のわれわれに投げかけるところが多々あるのではないかと思います。皆様の感想やつぶやきをお寄せください。
参考文献
・『レントゲンの生涯』W.Robert Nitske , 考古堂
・『孤高の科学者W.C.レントゲン』山崎岐男、医療科学社、1995
・『被曝の世紀』キャサリン・コーフィールド、朝日新聞社、
・『レントゲンとX線の発見』青柳泰司,恒星社厚生閣、2000
・『レントゲン』F.L.ネーエル、東京天然社、1943
・『レントゲン先生の生涯』新聞月報社、瀬木嘉一、1966
・『X線からクォークまで』エミリオ・セグレ、みすず書房、1982
・『医用X線装置発達史』青柳泰司
・『結晶とX線』H.S.Lipson、共立出版、1976
・『レントゲンの生涯、X線発見の栄光と影』山崎岐男、富士書院、1986
・ ウィキペディア、放射線障害の歴史、 http://jawikipedia.org/index.php?title
・『放射線と健康』館野之男、岩波新書、2001
・「新しい種類の線について(第1報)」W.C.レントゲン、1895
・「新しい線について(第2報)」W.C.レントゲン、1896
・「X線の性質についての観察の続き(第3報)」W.C.レントゲン、1897 ・McCulture’s Mgazine Vol16,No5,April,1896
TOPへ